この記事はこんな人におすすめ
- 医学研究や臨床研究に携わる医療従事者
- EBM(Evidence-Based Medicine:根拠に基づく医療)を実践したい医師や看護師
- 論文検索や臨床疑問を整理するフレームワークを探している人
- 医学部や大学院で研究手法を学んでいる学生
記事の概要
PICOとは、臨床疑問を整理し、エビデンスを効率的に検索するためのフレームワークです。
- P(Patient / Population):対象患者・母集団
- I(Intervention):介入
- C(Comparison):比較(対照群)
- O(Outcome):評価項目・アウトカム
研究課題を明確化し、論文検索の効率を高めるために用いられます。
この記事を読むと変わること(Before / After)
| Before | After |
|---|---|
| 臨床疑問が漠然としている | 4つの要素で明確に整理できる |
| 論文検索が効率悪い | PICOを使って検索式を構築できる |
| エビデンスの質を評価できない | 臨床に即したエビデンスを抽出できる |
PICOとは?(定義)
PICOは臨床疑問を「誰に、何をして、何と比べて、何を評価するか」で構造化するフレームワークです。
- P(Patient / Population)
- 例:高血圧の成人患者
- I(Intervention)
- 例:新しい降圧薬の投与
- C(Comparison)
- 例:従来薬の投与、プラセボ
- O(Outcome)
- 例:収縮期血圧の低下、心血管イベントの減少
この4つを組み合わせることで「臨床疑問(Clinical Question)」を具体化できます。
PICOの起源
- 1990年代、カナダのマクマスター大学を中心に発展した EBM(根拠に基づく医療) の教育で導入。
- Gordon Guyatt教授らがEBMの概念を体系化する中で、臨床疑問の定式化にPICOが活用されるようになった。
- 以来、世界中の医療教育・研究に取り入れられ、現在ではガイドライン策定やシステマティックレビューにも必須の枠組みとなっている。
PICOの活用事例
事例1:新薬の効果を調べる
- P:糖尿病患者
- I:新しい経口薬
- C:従来薬
- O:HbA1cの改善、低血糖発作の頻度
事例2:看護ケアの効果検証
- P:術後患者
- I:早期離床プログラム
- C:標準ケア
- O:合併症発生率、在院日数
事例3:公衆衛生分野
- P:中学生
- I:禁煙教育プログラム
- C:教育なし
- O:喫煙開始率
PICOのメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 明確化 | 臨床疑問を具体的にできる | シンプルすぎて複雑な疑問には不十分 |
| 検索性 | 論文検索式を組み立てやすい | PICOの定義が曖昧だと検索精度が下がる |
| 汎用性 | 医学だけでなく看護・薬学・公衆衛生に応用可能 | 定性的研究や探索的研究には向かない |
PICOのビジネス応用
1. マーケティング施策の検証
- P(Population)顧客層
→ 例:20代女性のオンラインショッピング利用者 - I(Intervention)施策
→ 新しいLP(ランディングページ)のデザインを導入 - C(Comparison)比較
→ 従来のLPをそのまま使用 - O(Outcome)成果
→ CVR(コンバージョン率)の改善
A/Bテストの設計に近く、PICOで整理すると検証の枠組みが明確になります。
2. 人事・組織開発
- P:新入社員
- I:メンター制度を導入
- C:OJTのみで研修
- O:定着率や早期離職率の改善
「制度導入が本当に成果につながったか」を比較可能に。
3. プロダクト開発
- P:既存ユーザー(例:アプリ利用歴1年以上)
- I:新しいUI/UX改善を導入
- C:従来のUIを維持
- O:利用時間の増加、解約率の低下
仮説検証型の開発(Lean StartupやMVP検証)にもPICOは役立つ。
4. 営業戦略
- P:中小企業の経営者
- I:コンサルティングパッケージA
- C:従来サービスB
- O:成約率・顧客満足度の向上
営業手法の比較検証にも応用可能。
PICOをビジネスに使うメリット
- 問いを明確化できる:「誰に」「何をして」「何と比べて」「どんな結果を狙うか」が整理される
- 施策の因果関係が可視化される:成果が「偶然」か「施策によるもの」かを切り分けやすい
- エビデンスベースの意思決定:直感や経験に頼らず、検証的に施策を進められる
PICOの応用形
- PECO:Exposure(曝露)を加え、観察研究に対応
- PICOT:Time(期間)を追加し、追跡研究に対応
- PICOTS:Study design(研究デザイン)を追加し、レビューやガイドラインに活用
よくある質問(FAQ)
Q1. PICOは医学以外でも使える?
→ はい。看護学、薬学、心理学、公衆衛生、ビジネスなど幅広く応用されています。
Q2. PICOを使うと論文検索はどう変わる?
→ キーワードをP・I・C・Oに分解して組み合わせることで、効率的に検索できます。
Q3. PICOが向いていない場面は?
→ 定性的研究や探索的研究など、「比較」が存在しない問いには不向きです。
まとめ
- PICOとは、臨床疑問をP(患者)・I(介入)・C(比較)・O(アウトカム)で構造化するフレームワーク
- 起源は1990年代のEBM教育で、Guyattらによって普及
- 新薬評価、看護ケア、公衆衛生まで幅広く活用可能
- 派生形(PECO、PICOT、PICOTS)もあり研究の種類に応じて使い分けられる

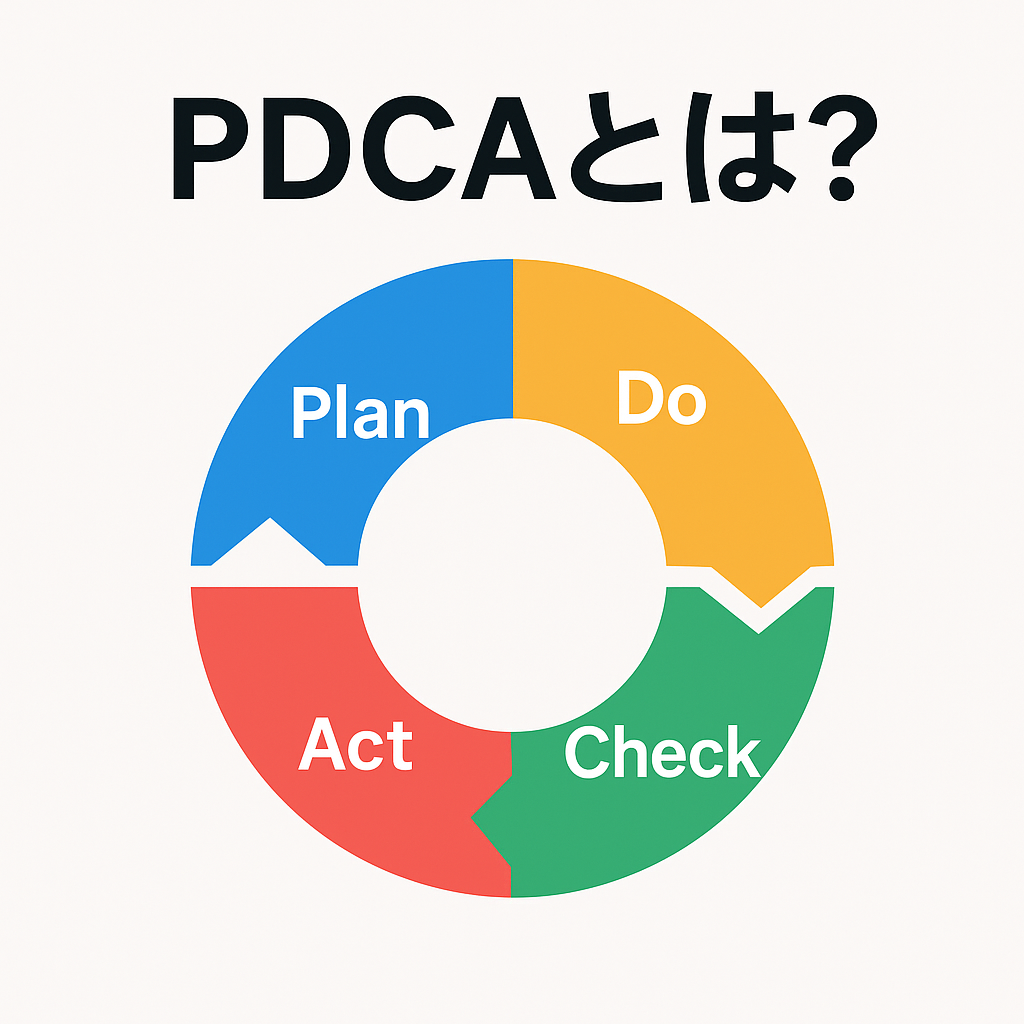
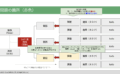
コメント