日本バドラー&コンシェルジェの代表取締役新井直之さんの書籍です。
世界のVIPをもてなすには「察する技術」が必要とのことでその身につけ方や技術が書かれています。
章は下記で構成されています。
第1章社内で「察する力」を鍛える
第2章社外で「察する力」を鍛える
第3章外出先で「察する力」を鍛える
第4章自宅で「察する力」を鍛える
特に印象に残った箇所を記載します。
定義:察する技術とは?
相手が何か言う前に、要望を察して行動に移すこと。つまり、一を聞いて十を知り、十二分のサービスを提供すること。または、不測の事態を察して滞りなく業務ができるようになる力です
はじめに・序章
- 察する技術は努力次第で誰にでも身につけられる
- 察する技術を身につけるには、3つの要素が必要
- 観察力、分析力、仮説力
- 観察力は、些細な変化を見逃さない力、相手が暗に発しているメッセージや主張を感じ取る力
- 分析力は、観察して得たものについて意味付けを考えたり、事柄を整理したり、順序立てて考えたり、まとめたりする力
- 仮説力は、観察・分析で集まってできた情報や考えから、未来を予測する力のこと
- 1度やったくらいでは身につかないので習慣化してはじめて身に付く
- 観察力は、常に「何か意味があるのでは?」と思いながら相手を観察することで初めて力がついていく
- 「物事にはすべて理由がある」という前提で考えること
- 仮説を立てる癖をつけるのが第一歩
第1章:社内で「察する力」を鍛える
- 仕事相手の持ち物で鍛える
- 見えるところに気を使っているか?
- TPOに合わせたものを選んでいるかどうか?
- 持ち物にこだわる人というのは多くの場合、相手の持ち物も観察している
- 値段よりこだわり度で誇り度を分析する
- 注意点
- 業種や職種によってこだわりは違う点
- 注意点
- アポイントの日時で鍛える
- アポイントを入れるときは「いつがいいですか?」と相手に漠然と聞くのではなく、候補の曜日・時間帯にバリエーションをつけて提示し、相手に選んでもらう習慣をつける
- 月曜日、金曜日の場合は真剣度が高い
- アポイントの基本
- 10時、13時、15時、17時
- いずれもあとの予定が入りづらい時間枠
- 逆に13:30分などは30分しか会いたくない気持ちの表れの可能性
- 10時、13時、15時、17時
- 仕事メールで鍛える
- 役職や秘書の連絡先がある場合は要注意
- 名刺で鍛える
- 書かれている情報と書かれていない情報を見極める
- 社内向けかお客様向けかが垣間見える
- 会議で鍛える
- 関係のない会議に出席すると冷静になれる
- 冷静になりスポーツ解説者気分で観察・分析する
- 写真で鍛える
- 家族(クライアント)写真を見える位置におく★
- 写真は思い出すきっかけ
- 見るたびに意識することができる
- 家族(クライアント)写真を見える位置におく★
- 身銭を切って鍛える
- 身銭を切ると視点が変わる
- 売る側から消費者側へ
- 身銭を切ると視点が変わる
第2章:社外で「察する力」を鍛える
- 色で鍛える
- 色と態度をセットで覚えておく
- イメージづくりで鍛える
- 具体的に聞く
- 相手のイメージとこちらのイメージを擦り合わせる作業
- 具体的に聞く
- 別れ際で鍛える
- 別れ際こそがゴールデンタイム
- 相手の言葉で鍛える
- 漠然と話しを聞いてはいけない
- 相手が何かをごまかすようなこと、明確でない言葉などを聞き逃さないということ
- 漠然と話しを聞いてはいけない
- 取引先で鍛える
- 3回目で本音がわかる
- 訪問する理由をつくる
第3章:外出先で「察する力」を鍛える
- 食器で鍛える
- 高価なものと安価なものを使っているときの差があるかを観察する
- 高価なものは丁寧に扱う傾向が高い
- セレブの情操教育にもなっている
- あえて子供に高い食器を使わせる
- 所作が丁寧になる
- 性格にも影響する
- 所作が丁寧になる
- あえて子供に高い食器を使わせる
- キッチンで鍛える
- 肥満になっている家庭は冷蔵庫に不要な食品が多い
- 冷蔵庫が大きいということはそれだけストックがあること
- 健康的な家庭はちょっとした残り物等がある
- 目につくところに食べ物を置かない★
- 手に取りやすくなる
- 健康な家庭は計画的に食べる
- 体重と冷蔵庫の大きさは比例する
- トイレで鍛える
- 経済状況の「今」が反映されやすい
- 個人宅だけではなく高級ホテルや旅館も同様
- 肥満になっている家庭は冷蔵庫に不要な食品が多い
- 本棚で鍛える
- 本棚はその人のプレゼンテーションの場である
- 相手の行動と本を関連づける癖をつける
- レストランで鍛える
- タダのものに手を抜くお店は美味しくない★
- 出されたお冷でだいたいがわかる
- タダのものまで気が回るのは余裕の表れ★
- タダの部分と有料の部分を比較検証
- タダで提供されたものには、提供した人、あるいは会社の本質体質が現れます
- タダで提供されたものと料理の味がリンクするかチェックする
- タダのものに手を抜くお店は美味しくない★
- ペットを見て鍛える
- 大人しくて人なつっこい犬なら、飼い主の家族はだいたい温厚
- 犬種を見るだけでも、飼い主の大まかな性格はわかる
第4章:自宅で「察する力」を鍛える
- 想像を働かせて鍛える
- 自分がいなくても相手は困らないか?と仮説を立てること
- 夫婦関係なら、「もしこの家から自分がいなくなったら」と考える
- あれ?いなくなっても困らないぞというのが見えてくる
- いなくなっても困らないのは、相手に対して何も貢献していないから
- あれ?いなくなっても困らないぞというのが見えてくる
- 休んでも意外に会社は困らない
- 解約時「もし私どもがいなくなったら」という仮説をたてる★
- 自分が思うほど相手はあなたのことを重要だと思っていない
- 自己否定を恐れない
- 食事のリクエストで鍛える
- 1つのことについて様々な角度から質問をする
- しつこく質問できる人ほど分析力は高くなる
- お仕えしている方が本当に何を考えているのか?そこを理解してから行動を起こしたほうがより万全の執事サービスを提供できる
- 質問が減る=カンがよくなる
- 以前は10個の質問で核心がわかったものが2つや3つの質問でわかってくる
- 相手のことを思って質問していることを伝える
- 慣れていないのに色々質問攻めするのはトラブルの元
- 立場を変えて質問をしていく
- 例
- 「焼き餃子が食べたい」
- 「大切な人友人に焼き餃子をごちそうするのはどんなときですか?」
- 例
- 執事サービスの仕事でも、お仕えする方から何かご依頼があった場合は、必ず3回は「なぜ」と聞くようにスタッフに行っている
- これでこそ、お客様が本当にのぞんでいることがわかる
- 相手からの質問には必ず意味がある
- 相手の意図をきっちりとらえるクセをつける
- 思考パターンを掴んで鍛える
- これでこそ、お客様が本当にのぞんでいることがわかる
- 1つのことについて様々な角度から質問をする
- 本で鍛える
- 仮説力は習慣化しないと身につかない
- マニュアルは繰り返し読ませる
- 項目は30項目弱。臨機応変な対応が求められる。
- 絶対に守ってくださいと執事には徹底している
- マニュアルを読み、項目の意味について考えてもらっている
- これは!という本に出会ったら最低でも3回〜5回は読む
- 読むたびに新しい発見がある
- いろいろな本の大元になっている名著から探す
まとめ
観省庵の「観」である観察力を研究するために読んだ1冊でした。ところどころその箇所は偏見じゃない?!と思うところもありますが、あくまで「仮説」を立てていくそして実行していくことが大事ということだと理解しました。わかるわかるという共感するポイントがありました。どれか1つでも実施していきましょう。★は個人的な実践ポイントとします。
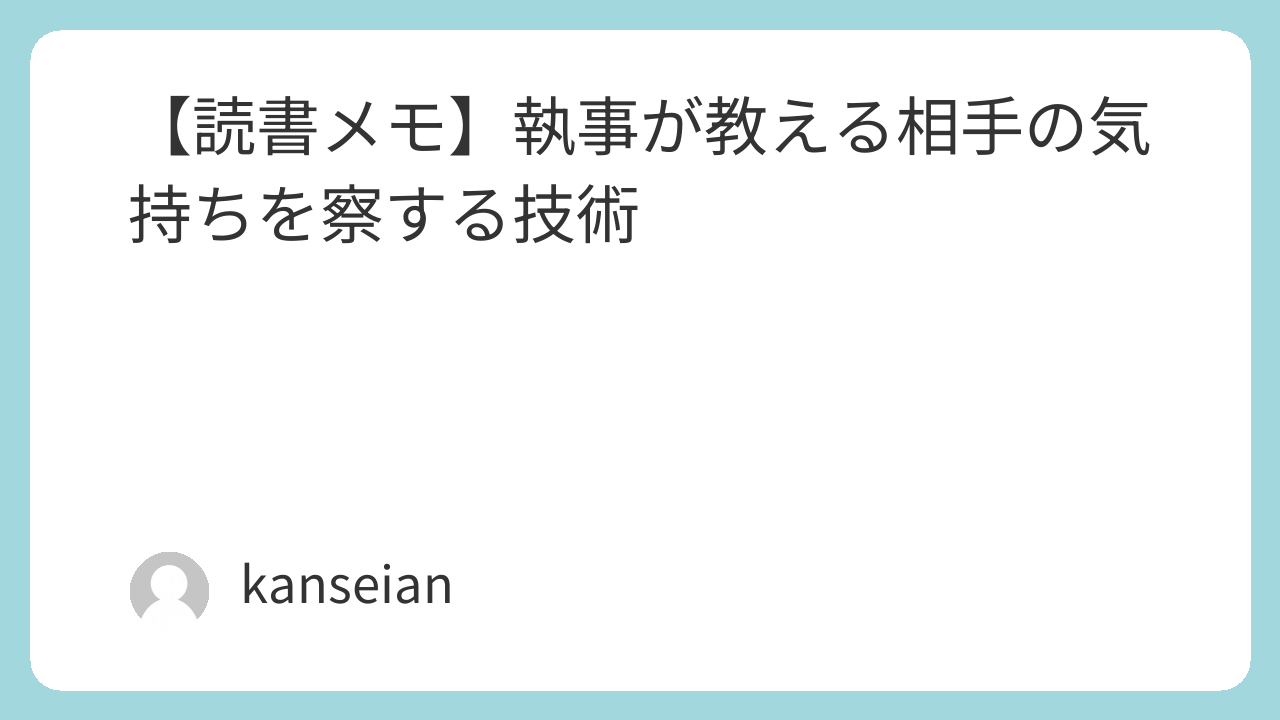
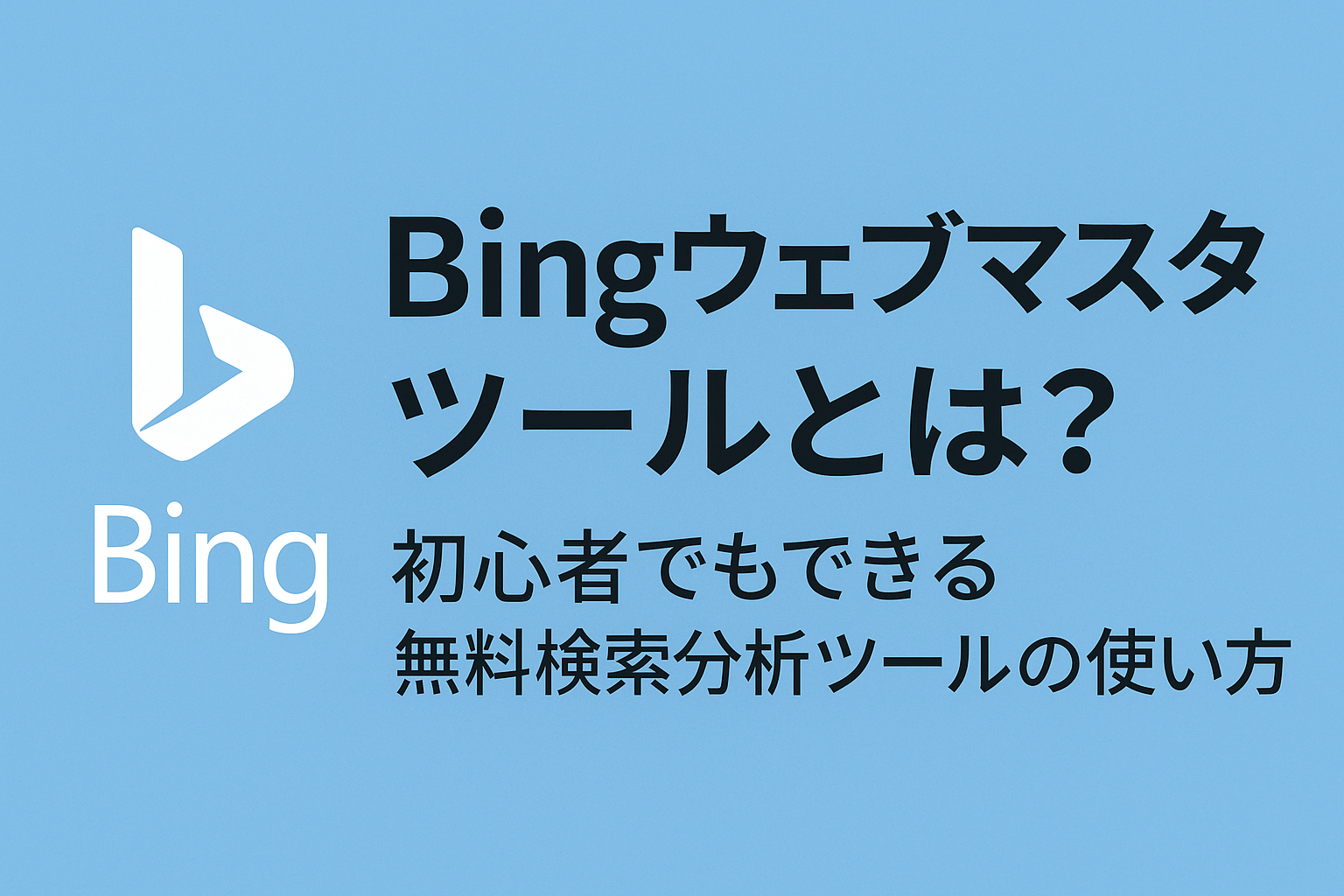
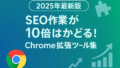
コメント