仮説の定義。これまで蓄積してきたメモをchatGPTに入れ整形しました。随時更新します。
仮説の定義
仮説とは:現時点で十分な裏付けがないものの、ある程度の根拠をもとに立てられた説明や予測の試み。仮説は「仮の説明」であり、検証や反証を通じて精度が高められる。
良い仮説 vs. 悪い仮説
| 評価軸 | 良い仮説 | 悪い仮説 |
|---|---|---|
| 反証可能性 | 反証が可能(具体的な証拠で否定できる) | 反証が困難(曖昧・検証不可能) |
| 反証コスト | 低コスト(容易に検証・否定できる) | 高コスト(検証に多大な資源が必要) |
| フィードバックの速さ | 速い(短期間で結果が出る) | 遅い(結果が出るまで時間がかかる) |
| フィードバックの正確性 | 高い(結果の信頼性が高い) | 低い(曖昧・ノイズが多い) |
| 信念の表現 | 確率などの形式で表現されている | 表現が曖昧、思い込みベース |
| 精度 | 高精度である可能性が高い | 低精度である可能性が高い |
| 仮説形成者の能力 | 十分な知識・経験を持つ人による | 知識・経験が乏しい人による |
仮説の種類
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 原因仮説 | 「○○の原因はAである」→ 情報収集・分析を通じて判定 |
| 解決仮説 | 「○○の解決策はBである」→ 実行とフィードバックを通じて判定 |
| 肯定仮説 | 「Aである」→ 状態や現象の存在を前提 |
| 否定仮説 | 「Aでない」→ 否定や非存在を前提 |
| 精度による分類 | 高精度仮説:知識や経験に基づく仮説 低精度仮説:思いつき・直感による仮説 |
| 段階による分類 | 初期仮説:仮説構築初期段階 中期仮説:一部検証済み 後期仮説:十分に検証され信頼性が高い |
仮説の形成
知識・経験の活用
→ 専門的背景や過去の事例をもとに仮説を立てる
主観的確率の付与
→ 各仮説に対して信念の度合いを数値で表す(ベイズ的思考)
※ 知識・経験が増えるほど、仮説の精度は高くなる。
仮説の検証方法
仮説が成立する条件・要因を調べる
仮説が成立しない条件・要因を調べる
※ 一般的に前者に偏りやすく、後者(仮説が成立しない条件)も意識することが重要
仮説の修正
新しい情報・視点に応じて、仮説に対する主観的確率を動的に更新する
ベイズ的思考(事後確率)による再評価が有効
仮説と実験の関係
仮説を検証するためには、「測定可能な結果を出す実験設計」が必要
観察・実験→データ収集→仮説修正・振り返りのループが重要(PDCAに類似)
仮説の利用シーン
ビジネス(意思決定・戦略仮説)
科学研究(因果関係・理論構築)
マーケティング(顧客行動・広告効果)
医療・教育・政策立案 など
全ての分野で応用が効く思考です。
仮説と直感・想像の違い
単なる直感やひらめきは「仮説」ではなく、「仮説」はあくまで検証可能性を伴う点が重要
おすすめ本『仮説思考』内田和成
仮説思考がなぜ重要かが分かりやすくまとめられています。
作業の時間を減らした方へおすすめです。
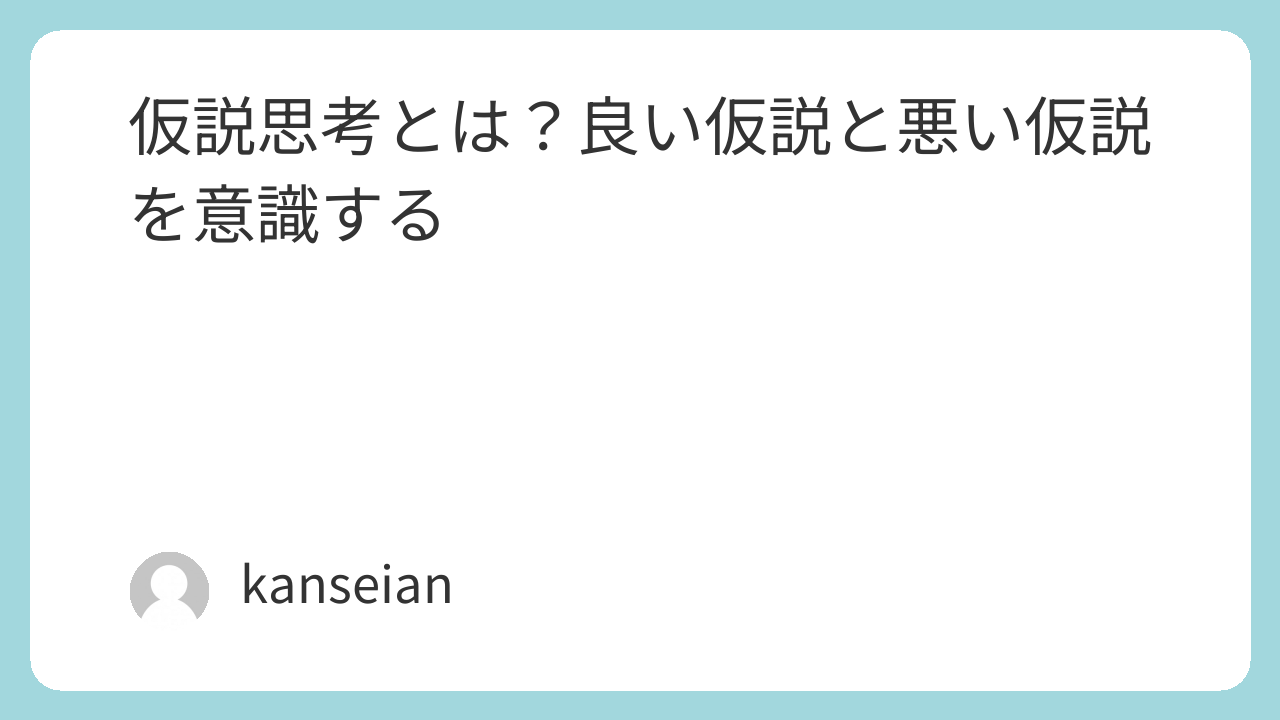
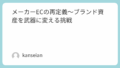

コメント