この記事はこんな人におすすめ
- マーケティングやブランド戦略に関わる方
- 「差別化」や「ロイヤル顧客育成」の常識に疑問を感じている方
- ブランドを成長させるために「何をすべきか」の科学的根拠を知りたい方
- 書籍『How Brands Grow(ブランディングの科学)』本の要点を短時間で把握したい方
記事の概要
本記事では、マーケティング科学者バイロン・シャープが提唱する「ブランド成長の法則」をわかりやすくまとめます。従来の「顧客ロイヤルティ重視」や「ターゲティング中心」の考え方に真っ向から反する内容に、多くのマーケターが衝撃を受けています。
この記事では、11の法則と2つの重要概念「メンタルアベイラビリティ」と「フィジカルアベイラビリティ」に触れ、実務に活かせるポイントを整理します。
この記事を読むことで変わること(Before / After)
| Before(読む前) | After(読んだ後) |
|---|---|
| 差別化・ロイヤルティが重要だと思っている | ブランド成長には「広く・浅く」が効果的と理解できる |
| 狭いターゲット層を狙うのが正解だと思っている | ライトユーザーを含めた「全体市場」を重視する意識に変わる |
| 継続購入者だけを大事にすればよいと思っている | 「非利用者への認知拡大」こそが成長戦略だと理解する |
『ブランディングの科学』とは?
『ブランディングの科学(How Brands Grow)』は、バイロン・シャープ(Byron Sharp)によるマーケティングの実証研究書です。長年の消費者行動データとマーケティング分析に基づいて、「ブランド成長のメカニズム」を科学的に明らかにした一冊であり、「マーケティングの通説に真っ向から反論する」として多くの注目を集めました。書籍の中では、コトラー本の内容を真っ向から否定している箇所もあります。
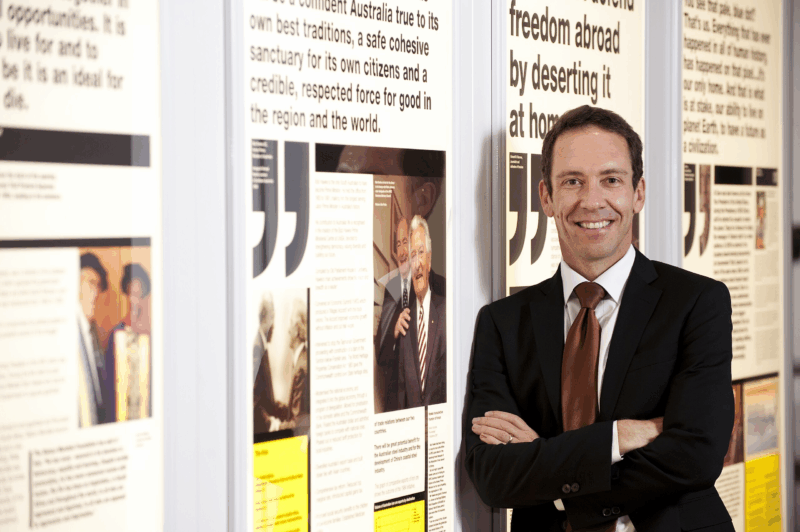
画像はWikipediaより引用
個人サイトは下記
11のマーケティングの法則とは?11のマーケティングの法則(『ブランディングの科学』)
バイロン・シャープが提唱するマーケティングの科学における11の法則(主に『How Brands Grow』第1巻に基づく)は以下のとおりです。
- ダブルジョパディの法則
- リテンション・ダブルジョパディの法則
- パレートの法則
- 購買行動適正化の法則
- 自然独占の法則
- 顧客基盤が類似する
- ブランドに対する態度と使い方が行動的ロイヤルティに反映される
- ブランド使用体験が態度に影響を与える
- プロトタイプの法則
- 購買重複の法則
- NBDディリクレ・モデル
11の法則の簡単な解説と英語名
特に知りたい法則は英語名で検索すると多くの記事がでてきますので参考にしてください。
| # | 法則(日本語訳) | 原典でよく使われる英語名 | エッセンス一言 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブルジョパディの法則 | Double-Jeopardy | シェアが小さいブランドは「買う人も少なく、ロイヤルティも低い」二重の不利を受ける。 |
| 2 | リテンション・ダブルジョパディの法則 | Retention Double-Jeopardy | シェアが小さいブランドは「失客率も高い」ため、維持でも不利を背負う。 |
| 3 | パレートの法則(60/20 ルール) | Pareto (60/20) | 上位20%顧客が売上の約60%を生む。80/20 ほど極端ではない。 |
| 4 | 購買行動適正化の法則 | Law of Buyer Moderation | ヘビーバイヤーは次期に減り、ライトバイヤーは増える傾向(平均への回帰)。 |
| 5 | 自然独占の法則 | Natural Monopoly | 大ブランドほどライトユーザーを多く抱える。 |
| 6 | 顧客基盤が類似する | Customer Base Similarity | 同一カテゴリのブランドは顧客構成が驚くほど似る。 |
| 7 | 態度と想いが行動ロイヤルティに反映される | Attitude-Behaviour Loyalty | “好き”と言う人ほど購買頻度が高いが、これはビッグブランドでは絶対数が多いだけ。 |
| 8 | ブランド使用体験が態度を与える | Experience-Drives-Attitude | 使った経験がブランド好意を高める。好意が先ではなく結果の場合が多い。 |
| 9 | プロトタイプの法則 | Prototypicality | カテゴリらしさを体現するブランドは想起されやすく、選ばれやすい。 |
| 10 | 購買重複の法則 | Duplication of Purchase | あるブランドの顧客が他ブランドも買う確率は、他ブランドのシェアで説明できる。 |
| 11 | NBDディリクレ・モデル | NBD-Dirichlet Model | 購買頻度・重複など消費者行動を数理的に一括説明する統合モデル。 |
2つの重要な法則
メンタルアベイラビリティ(Mental Availability)
購入の「場面(シチュエーション)」で自ブランドを思い出してもらえる可能性のこと。消費者の記憶の中で「選択肢のひとつ」に入ることが重要
フィジカルアベイラビリティ(Physical Availability)
購入したいと思った時に「すぐ買える状態」にあること
チャネル戦略、流通、在庫、立地、EC対応などすべてがここに含まれる
以下の2点の問いかけを大事にしてください。(観省庵思考メモ)
・顧客は、心の中であなたの商品/サービス/ブランド名思い出せるか?
・顧客は、あなたの商品/サービス/ブランド名は手に入りやすいか?
個別解説 & 実務へのポイント
1. ダブルジョパディの法則
- 概要
小ブランドは「顧客数(浸透度)×ロイヤルティ」の両方で不利。 - 示唆
“ファン化”よりまず浸透度(Penetration)拡大に注力。マスリーチ施策が基本。
2. リテンション・ダブルジョパディの法則
- 概要
顧客離脱率はシェアに反比例。大ブランドは数字上多く失客しても割合は低い。 - 示唆
CRMで小ブランドの離脱率を劇的に下げるのは難しい。新規流入とのバランス設計が重要。
3. パレートの法則(60/20)
- 概要
売上の約60%は上位20%顧客が生む。ただし残り40%も無視できない。 - 示唆
VIPプログラムだけでなく、多数のライトユーザー施策(試買・リピート促進)も並行。
4. 購買行動適正化の法則
- 概要
ヘビーバイヤーは次期に購買量が減り、ライトバイヤーは増えやすい“平均への回帰”。 - 示唆
直近購買量だけで顧客クラスタを固定せず、期間を跨いだ動きをウォッチする。
5. 自然独占の法則
- 概要
市場シェアが大きいブランドほど、カテゴリ全体のライトバイヤーを多く獲得する。 - 示唆
規模拡大で“たまに買う層”も巻き込める。流通カバレッジや在庫露出を広げる投資が回収しやすい。
6. 顧客基盤が類似する
- 概要
性別・年齢・心理態度など、競合同士の顧客分布は驚くほど似ている。 - 示唆
極端なポジショニングで「○○専用ブランド」を作ろうとしても市場は狭い。
“誰でも買えるブランド”を前提に差別資産(Distinctive Assets)を積み上げる。
7. 態度と思いが行動ロイヤルティに反映される
- 概要
“好き”という態度は購買頻度と相関。ただし大ブランドは人数が多いだけで好意度が特別高いわけではない。 - 示唆
好意度スコア比較はシェア補正を忘れずに。ブランド追跡調査に購入行動の併記が必須。
8. ブランド使用体験が態度を与える
- 概要
消費者は使用経験の有無でブランド好意が変わる。態度→行動ではなく行動→態度の因果も大きい。 - 示唆
無料サンプル・トライアルが態度形成に効く。体験後フォローで好意を固定化。
9. プロトタイプの法則
- 概要
カテゴリの代表的イメージ属性(色・形・用途など)と合致するブランドは想起率が高い。 - 示唆
「奇をてらう差別化」よりカテゴリらしさ+独自アセットの掛け算が想起を促す。
10. 購買重複の法則
- 概要
任意ブランドAの顧客がブランドBも買う確率 ≈ ブランドBの市場シェア。 - 示唆
クロスセル狙いのブランド組み合わせはシェア規模でほぼ決まる。
共通顧客が多い=競争が激しい、とは限らない。
11. NBDディリクレ・モデル
- 概要
「何人が何回買うか」「競合ブランドをどれだけ重複購入するか」を同時に予測できる確率モデル。 - 示唆
新商品導入やキャンペーン後の売上予測ベンチマークとして活用可能。
異常値を検知し「本当に効果が出たのか」「一時的なブレか」を判断する物差しになる。
どう使うか:実務的チェック観点
- KPI設計
- 浸透度(Penetration)を主要KPIに入れる。
- ロイヤルティ指標は「ファン化」より「平均購買頻度」で把握
- 浸透度(Penetration)を主要KPIに入れる。
- メディア配分
- 同一ターゲティングで狭く最適化し過ぎない。ライトユーザーに届く媒体を一定比率確保。
- リサーチ
- 好意度調査は経験者/非経験者を分けてクロス集計。
- ブランド間の態度差を議論する際はシェア補正を忘れない。
- 計画評価
- キャンペーン後の売上・シェア変化を NBDディリクレ予測と突き合わせ、統計的に検証。
ブランディングの科学』の注意点
BtoCマスマーケティング前提
- 本書はFMCG(消費財)や大規模ブランドのマスマーケティングを前提にしています。
- BtoBや高関与商材(例:高級車、不動産など)にはそのまま適用できない部分もあります。
- BtoBの場合はABM(AccoutBasedMarketing)が重要とされていますし、消費者の購買ロジックが変わってくるため適用のしにくさがあると思われます。
ロイヤルティ戦略を否定しているわけではない
- 「ロイヤル顧客は少なく、ライトユーザーが重要」と述べていますが、
ロイヤルティ施策が不要とは言っていません。 - 顧客維持と獲得のバランスの最適化が重要だと再解釈するのが妥当です。
差別化軽視の誤解に注意
- 「差別化は重要ではない」と読めてしまいますが、実際には認知可能な差異(Distinctive Assets)の構築を強調しています
- 「差別化ではなく、類似性+記憶資産による“思い出されやすさ”がカギ」
短期的な効果ではなく中長期視点
- 認知や購入行動の変化は時間がかかるため、即効性は期待できません。
- 目先の反応率ではなく、ブランドの記憶構造づくりを重視するべきです。
従来の「ポジショニング理論」との対立構造
- アル・ライズ&ジャック・トラウトの「ポジショニング」やコトラーのSTP戦略とは異なる思想。
- 二者を対立ではなく、併用可能なフレームとして捉えることが現実的。
なんでもそうですが、全てを解決できる法則はないので、適材適所で道具として利用することが大事です。限られた状況でのエビデンスという姿勢が大事です。
まとめ
・バイロン・シャープの『ブランディングの科学』は、マーケティングの「思い込み」を打ち砕き、ブランド成長における“科学的に正しい”方向性を示してくれます。
・「差別化よりも記憶資産」「ロイヤルカスタマーよりライトユーザー」「ターゲティングよりリーチ」がブランド成長のカギ。
・本書の内容を実務に落とし込むことで、マーケティングの解像度は一段と上がるはずです。ぜひ下記本を一読してみてください。
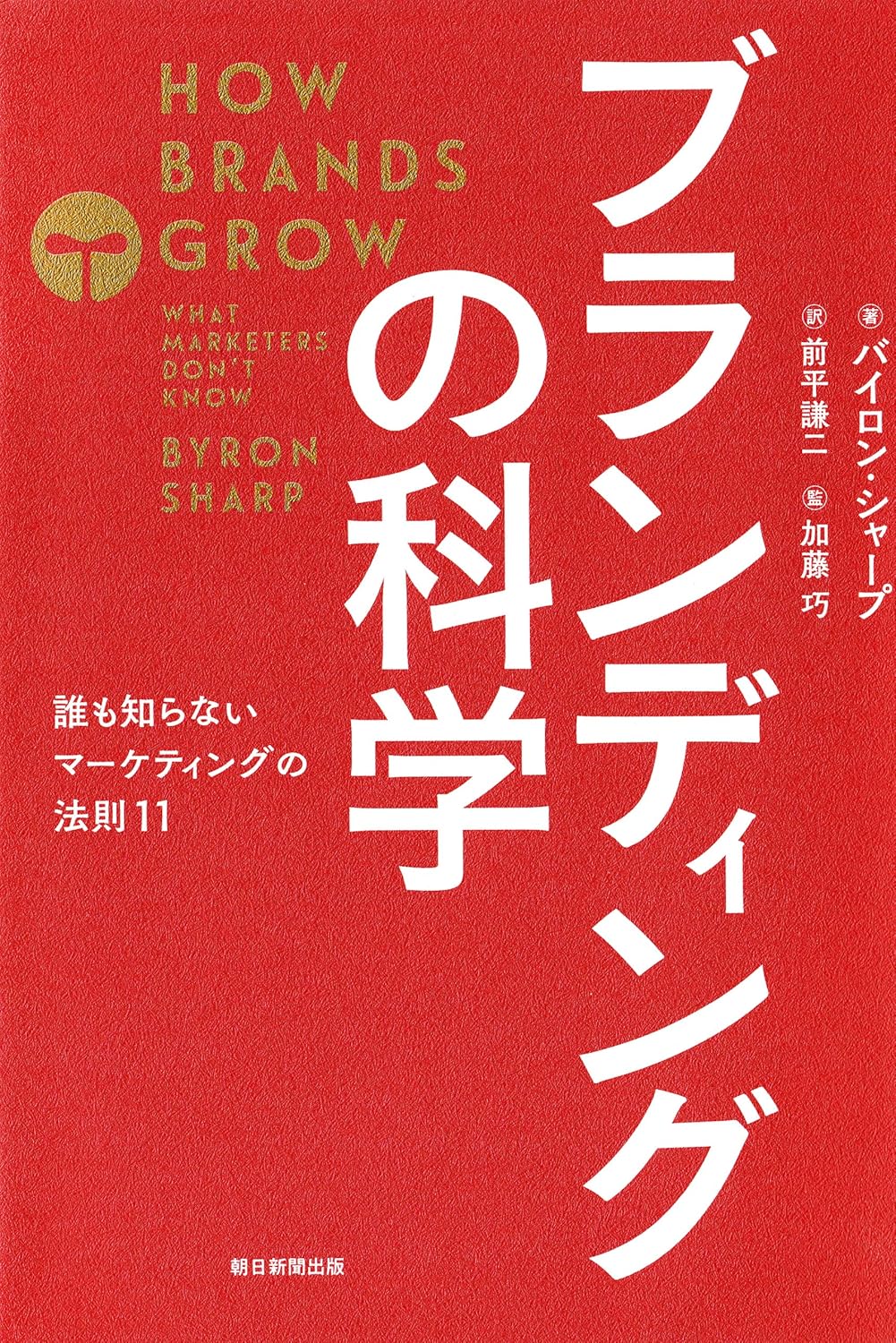


コメント