こちらは、 Harvard Business Review ポッドキャスト「HBR On Strategy」のエピソード “The Right Way to Make Data-Driven Decisions”(2025年3月5日配信)を整理した内容です。
本エピソードでは、 Michael Luca(ジョンズ・ホプキンス大学ケアリー経営大学院)と Amy Edmondson(ハーバード・ビジネス・スクール)が “データ駆動型の意思決定” がうまくいかない理由と、その改善のためのフレームワークを紹介しています。以下、ポイントを整理します。
概要
- 組織は「データを使った意思決定」にますます注力しています。
- ただし、データを 持っているだけ/分析しているだけ では十分ではなく、どのように「解釈」「活用」するかが意思決定の質を左右します。
- Luca/Edmondson は、社内データ・社外データを問わず、よくある落とし穴を整理し、良い意思決定を支えるための「問いかけのフレームワーク」を提案しています。
主なテーマと論点
1. 内部データ vs 外部データ
- 外部データ:学術研究や他社の実験など「他の文脈で得られた知見」。これを自社に「移植」する際、
- そもそもその研究・実験が 妥当に実施されていたか(内部妥当性)
- その研究・実験の文脈が自社とどれだけ似ているか(外部妥当性/一般化可能性)
を検討する必要がある
- 内部データ:自社が保有・生成しているデータ。実験やA/Bテストなどで得られることも多いが、
- 測定している “指標” が本当に「自社が追いたい成果」なのか
- 測れていない “副次的な影響” はないかが見落とされがち
- 両者を 組み合わせて議論すること が、よりよい意思決定に繋がる。
2. よくある落とし穴
- 因果関係 vs 相関関係:データ上で「この要因がこの結果を引き起こした」と言えるかを見極めることが重要。
例えば、 eBay の広告実験では、広告を出した地域で売上が上がっていたが、それは広告のおかげではなく「そもそも買う人が多かった地域」だったという分析が示されています。 - 測定するものと、追いたい成果がずれている:実験で「訪問数が増えた/クリック数が増えた」としても、「長期的な顧客維持」「ブランド価値の向上」「顧客満足度」が追えていない場合、真の成果とズレが生じる可能性があります。
- サンプルサイズ・統計的検出力の問題:例えば「売上が5 %増えた」という結果が出ても、サンプルが小さければその増加が偶然の範囲内ということもある。
- 一般化可能性(外部妥当性)の誤判断:ある企業・ある状況で得られた結果を、自社のまったく異なる状況にそのまま当てはめてしまうのは危険。
3. フレームワーク:問いを立てて議論すること
Luca/Edmondson が提案するのは、「ただデータを眺める」ではなく、「問いを立て、仮説を検証し、議論する」文化を持つこと。具体的には:
- この分析で 何を測っているか? 本当に自社の追いたい成果と整合しているか?
- その分析で どんな仮定があるか? どんなデータ・設定からこの結果が導かれているか?
- その結果が出た 文脈/条件 は何か? 自社の状況とどのくらい似ているか?
- 結果の 不確実性・ばらつき(例:信頼区間) はどうか? どこまで施策に反映するか?
- 副次的な影響/未測定の影響(=「測ってないけど重要かもしれないこと」)はないか?
- これを受けて次に 何を試すか? どのように反復・学習していくか?
また、組織文化としては、「知らないことを許す/学ぶことを尊ぶ*態度が重要。すぐに答えを出すことより、「このデータから何が分かるか・何がまだ分からないか」を議論できる対話環境が望ましいとしています。
4. 意思決定者・マネージャーに求められる能力
- 全ての人がデータサイエンティストになる必要はないが、データサイエンティストとマネージャーが 対話できる共通言語・共通フレーム を持つことが望まれる
- マネージャー/リーダーとしては、議論をリードできる“ファシリテーション力”、そして議論を安全に行える“心理的安全性”を担保することが重要
- データに基づく意思決定とは「完璧な答えを出すこと」ではなく、「より良い仮説・より良い選択を、限られた不確実性下で行うこと」である、というマインドセットが必要
まとめ:実践のためのチェックポイント
- 分析を使う際には、「このデータ/分析は、私たちの意思決定すべき問いに対して妥当か?」を必ず確認する。
- 因果か相関か、測ってる指標は目的に沿っているか、サンプルサイズ/信頼区間はどうか、一般化できるか、未測定の影響はないか…など、問いを立てて議論すること。
- 組織として、データを “神格化” しすぎず、「疑問を持てる」「学び続けられる」姿勢を文化に持つこと。
- 会議・議論では「これは仮説検証の場」「学びの場」としてスタートすることをリーダーが宣言するのが効果的。
- 小さな実験・反復を通じて、データから学び、次のアクションに繋げていく。大規模投入を考える前に “試し・学び” を重ねる。

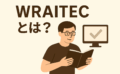
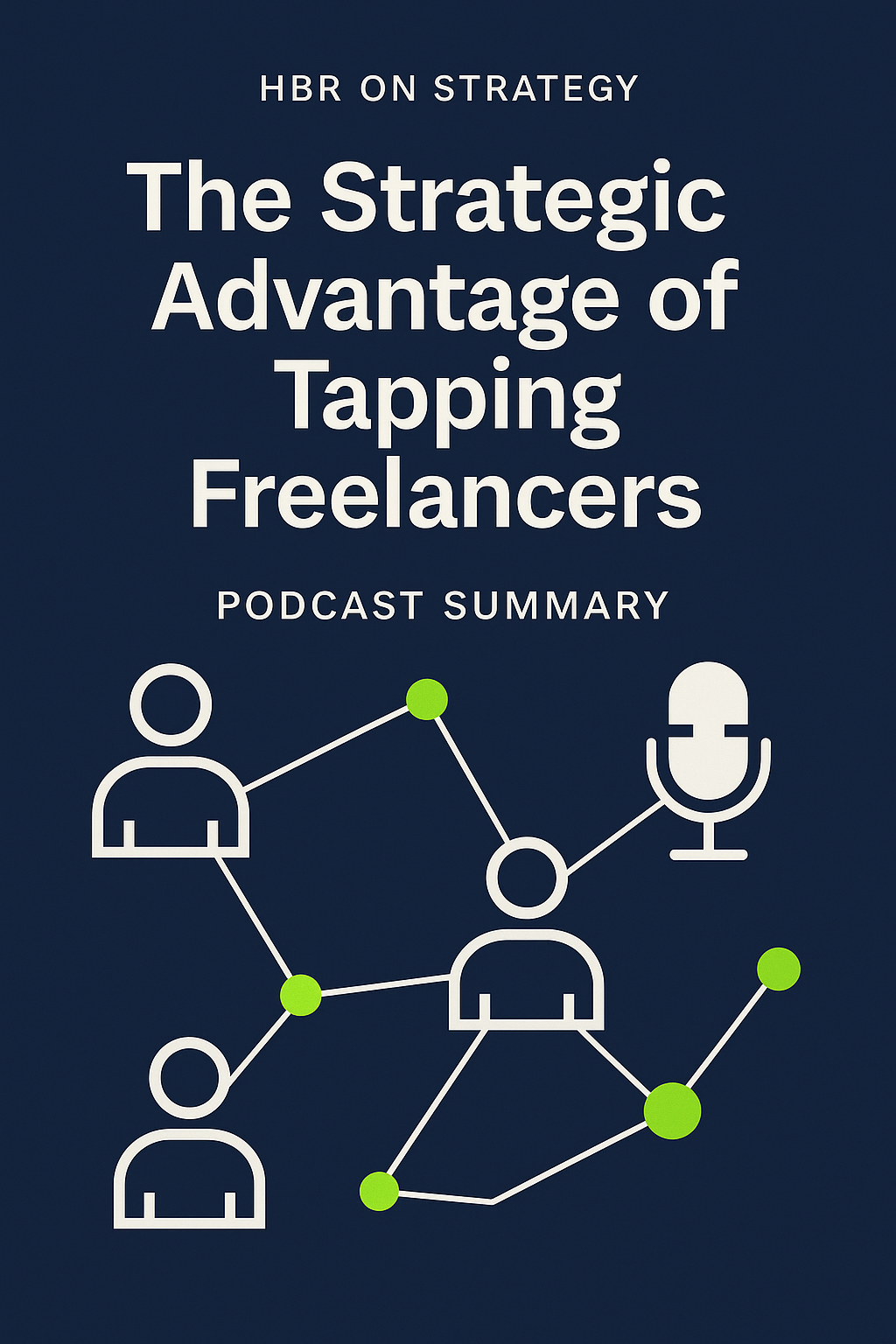
コメント