※下記はGPTのDeepResearchに紐づくものです。
リフレクションとは何か:目的と意義
リフレクション(reflection)とは、単なる「反省」や「後悔」とは異なり、自身の経験を振り返りその意味や学びを深めるプロセスを指します。1教育哲学者デューイは「人は経験から直接学ぶのではなく、経験を振り返り考察することで学ぶ」と述べ、経験全体を言語化し判断を再考する重要性を説きました。リフレクションの目的は、過去の体験から教訓や洞察を得て将来に活かす「意味づけ(センスメーキング)」にあります。したがって評価や原因追及だけが目的ではなく、ポジティブな出来事も含めて経験全体を客観的・建設的に見直し、未来志向で学びにつなげる点が特徴です。リフレクションにより、自分でも気づかなかった価値観や信念を発見し、自己の成長につなげる効果が期待できます。
また、「反省」(hansei)との違いとして、反省が過ちの是正に焦点を当てがちなのに対し、リフレクションは成功体験も含め客観的に振り返り未来の行動に教訓を活かす点にあります。たとえば「大成功を振り返る」こともリフレクションに含まれ、失敗・成功双方から学びを引き出します。このプロセスでは自責や他責に陥らず事実ベースで冷静に自己対話することが重要であり、他者から強制されるのではなく主体的に行う点もポイントです。
リフレクション技法の実践方法と訓練法
個人でのリフレクション:リフレクティブジャーナルと内省
個人でリフレクションを行う代表的な方法に、リフレクティブジャーナル(内省日誌)があります。日々の経験を文章に書き出し、何が起こり自分はどう感じ考えたか、そこから何を学んだかを綴ることで、経験を客観視し深い洞察を得ることができます。ジャーナルを書く行為自体が思考を整理し、気づきを促進する効果があります。
また、個人での内省では「What?(何が起きたか)」「So what?(それはどういう意味か)」「Now what?(次にどう活かすか)」といったガイド質問を自分に投げかける手法も有効2です。
例えばBortonやDriscollによるこの3段階の問いかけモデルはシンプルながら効果的で、初学者でも取り組みやすいと言われます。
さらに、チェックリストや定型フォーマットを用いることで内省を体系立てることもできます。ジョンズ(Johns)の構造的内省モデルでは18項目にも及ぶ質問リストが提示され、問いに答えていくことで自然と深い省察に導かれるよう工夫されています。このような質問リスト型のモデルは、自分では気づきにくい視点を提供してくれる反面、質問に従うだけでは受動的になり自律的な思考が妨げられる恐れも指摘されています。したがって、個人でリフレクションを行う際はガイドとなる枠組みを活用しつつも、自らの言葉で考察を深める姿勢が大切です。
グループでのリフレクション:対話とコーチング
リフレクションは個人作業だけでなく、グループでの対話によってさらに学びが深まることが多くの研究で示唆されています。グループリフレクションでは、まず各自が経験を書き出し内省した上で、それを他者と共有し対話するプロセスを取ると効果的です。例えば企業研修や看護師の院内研修では、研修参加者に体験を書かせた後、小グループで対話し学びを言語化させる手法が取られています。このとき重要なのは、安心して話せる場づくりと建設的なフィードバックです。対話では他者の視点からのフィードバックや共感を得られ、自分一人では気づかなかった視点に気づくことができます。
グループリフレクションを円滑に行うため、ファシリテーター(進行役)やコーチが付くこともあります。ファシリテーターは場を設定し、参加者に適切な問いかけをしたり、否定的な批評ではなく学びに繋がるフィードバックを促したりする役割を担います。
特に企業の1on1ミーティングやコーチングの場では、コーチが質問を投げかけながらクライアント自身の内省を深める支援を行います。ファシリテーターやコーチはリフレクションの目的が問題解決ではなく意味の発見にあることを理解し、参加者が安心して思考できる雰囲気を作ることが重要です。
このように、他者との対話はリフレクションを深化させ、新たな洞察や学習の定着を促す強力な手段となります。
リフレクションの主要なモデル(理論的枠組み)
リフレクションを体系的に行うため、これまでに多くの理論モデルが提唱されてきました。その中でも代表的なものとして、コルブの経験学習モデル、ギブスの反省サイクル、そしてショーンの省察的実践論があります。
コルブの経験学習モデル
- コルブの経験学習モデル(Experiential Learning Model):教育学者デビッド・コルブは、経験に基づく学習プロセスを4段階のサイクルで説明しました。
- そのサイクルは
- 「具体的な経験」→「省察的観察(内省)」→「抽象的概念化」→「能動的な実践」の順に進行し、継続的に循環します。
- たとえば、
- 仕事上のある出来事(具体的経験)を振り返り観察することで気づきを得(内省)、それをもとに一般化した教訓や理論を導き出し(概念化)、次の行動計画に落とし込んで試行する(実践)――という流れです。
- このモデルでは特に「内省的観察」の段階が重要な位置を占め、経験を振り返り分析することで初めて深い学習が生まれるとされます。
- コルブ自身「学習とは経験が変容され知識となる過程である」3と述べており、リフレクション(内省)は経験を知識に昇華させる要となっています。
- コルブの循環モデルは教育からビジネス研修まで広く採用されており、学習者が4つの段階をバランスよく踏むことで効果的に学べることを示唆しています。
ギブスの反省サイクル
- ギブスの反省サイクル(Gibbs’ Reflective Cycle):グラハム・ギブスは1988年に、経験から体系的に学ぶための6段階のリフレクションモデルを提唱4しました.
- ギブスのサイクルは
- (1)経験の記述**、(2)その時の感情、(3)評価(うまくいった点・いかなかった点)、(4)分析(要因や背景の考察)、(5)結論(得た教訓や今後変えるべき点)、(6)行動計画(今後同じ状況でどう行動するか)というステージで構成されます
- このモデルに沿って自問していくことで、経験を多角的に検討し、単なる反省に留まらず次につなげる具体策まで導き出せるのが特徴です。
- ギブスのモデルは、例えば看護や教育の現場で学生や新人が自己の実践を振り返る際によく用いられます5。手順が明確なため初心者にも実践しやすく、経験学習を再現可能なプロセスとして提供するものと評価されています。
- 一方で、サイクル型モデル全般の指摘として「現実のリフレクションは必ずしも段階的・循環的に進むものではない」「目の前の出来事や行動に意識が向きすぎ、背後の文脈や前提への省察が不足しがち」といった課題も論じられています。そのため、ギブスの枠組みを柔軟に捉え、必要に応じて質問項目を取捨選択することも推奨されています。
ショーンの省察的実践論
- ショーンの省察的実践論(Schön’s Reflective Practice):ドナルド・ショーンは『省察的実践家(Reflective Practitioner)』において、専門職が実践現場で知識を創造的に適用する過程としてリフレクションを位置づけました。
- ショーンは特に、専門家が予測困難で不確実な状況に対峙したとき、その場で試行錯誤しながら考えるプロセスに注目し、これを「行為の中の省察 (reflection-in-action)」と名付けています
- これは、実践中に頭の中で即興的に行う内省であり、状況に応じて自らの行動を調整していく柔軟な学習プロセスです。
- またショーンは、行為が終わった後で振り返る「行為についての省察 (reflection-on-action)」も重要だとしました。
- 例えば教師や看護師が授業やケアを提供した後で「何がうまくいき、何が課題だったのか」を振り返り、次の実践に活かすといった行為です。
- ショーンの理論は、単に理論知識を現場で適用するだけではなく、現場での経験から新たな知見や問いを生み出す循環としてリフレクションを捉え直した点に意義があります。これにより、専門職教育では知識・技術の習得だけでなく、変化の激しい実践状況に対応し課題を設定して解決策を探る「省察的実践家」の育成が重視されるようになりました。
- ショーン以降、教育学者コルトハーヘンは「リフレクションは理論と実践を結ぶ架け橋である」と述べ、実践知と形式知の往還を促す方法論としてリフレクションが位置づけられています。
- その他のモデルや枠組み:
- 上述の他にも、リフレクションには様々なモデルがあります。例えばブルックフィールドは教育実践における4つの視点(自己、学生、同僚、理論)から振り返る「クリティカルフレンド」モデルを提唱しました。
- またデューイ自身は1933年に問題解決の5段階(困惑-問題定義-解決策提案-推論-検証)を示しており、これは内省のプロセスを初期に体系化した例と言えます。加えて、リフレクションの深さの段階モデルとしてHatton & Smith (1995)の4レベル分類も知られています。そこでは「単なる記述的振り返り(出来事をそのまま記録)」「記述的内省(感じたことをそのまま記す)」「対話的内省(自身の役割や他事例との比較を分析)」「批判的内省(より広い社会文化的文脈まで踏まえて多面的に分析)」という階層が示され、より高次の内省ほど前提や文脈への批判的考察が含まれるとされます。
- このような階層モデルは、初心者がどの深さで内省しているかを評価したり、より深いレベルへの発達を促す指標として活用されています。一方で、現実の内省は必ずしも直線的に深まるわけではないため、教育の現場ではサイクル型モデルや質問リスト型モデルと組み合わせて指導に用いられることが多くみられます。
効果的なリフレクションの進め方とチェックリスト
リフレクションを効果的に行うためには、上記モデルに沿って適切な問いかけを自分に行うことと、素直な自己分析が大切です。例えばギブスのモデルであれば、「何が起きたのか?」「その時自分は何を感じ考えたか?」「うまくいった点・いかなかった点は?」「なぜそうなったのか?」「そこから得た教訓は?」「今後どう行動を改めるか?」といった問いを順に自問していくことで、体系的に経験を振り返ることができます。
このようなチェックリスト的問いかけにより、感情的な反応や思い込みに流されず、事実と解釈を区別して考察する習慣が養われます。実際、リフレクションの達人ほど無意識に「今回の経験から何を学べるか?」といった問いを自らに投げかけているものです。
また、チェックリストを使う際は形式的になり過ぎないよう注意が必要です。リストの質問にただ答えるだけではなく、そこで浮かんだ考えをさらに掘り下げてみたり、必要に応じて順番を入れ替えたりと、柔軟に思考を巡らせることが大切です。例えば「なぜそう感じたのか?」という問いに対して答えた後、さらに「その背景にはどんな信念や知識が影響しているだろう?」と自問することで、より深い内省につなげることができます。場合によっては同僚やメンターに自分への質問を投げてもらい、第三者の視点からの問いでハッと気づかされることもあるでしょう。
効果的なリフレクションには定期的な習慣化も重要です。週末や月末に一週間・一ヶ月を振り返るための時間をスケジュールに組み込み、チェックリストに沿って内省することで、日常業務に忙殺されがちな中でも継続して学びを得ることができます。例えば「月末リフレクションシート」を用意し、達成できたこと・できなかったこと、その要因、次月への活かし方を書くようにすると、PDCAサイクルの「Check」に深みが増します。このように構造化された内省を習慣付けることで、経験が確実に糧となり、個人の成長サイクルが回り始めるのです。
リフレクションに関する主要な研究と応用分野
教育分野におけるリフレクションの研究と実践
教育の分野では、リフレクションは教師教育や生涯学習において重要なテーマとなっています。教師志望者や現職教師が自らの授業実践を振り返り、より良い指導法や教師としての信念を醸成するためにリフレクションが取り入れられてきました。ドナルド・ショーンの影響もあり、1980年代以降「省察的実践家」としての教師像が提唱され、教師教育カリキュラムには授業後の振り返り記録や教師日誌、ポートフォリオ作成などが組み込まれるようになりました。これらは単に教え方を改善するだけでなく、教育理論と実践をつなぐ架け橋として機能し、教師が現場の経験から教育観を形成していくことを促す狙いがあります。
実証研究の面では、リフレクションが教師や学生にもたらす効果やプロセスが数多く検討されています。例えばHatton & Smith (1995)の研究では、教師志望者のリフレクション記述を分析し、大半が初めは出来事を羅列する記述的レベルに留まるものの、指導と時間を通じて自己の思考を問い直す対話的・批判的レベルへ深化していくことが報告されています。これに基づき、教師教育では学生に対し批判的リフレクション(自らの実践を社会的文脈や価値観まで踏まえて検討する深い内省)を促す指導法が模索されています。近年(2010年以降)は特に、リフレクションの社会的次元に注目が集まっています。単独での日誌記録だけでなく、ピアレビュー(相互批評)や協働的省察の場を設けることで、より多面的で客観的な振り返りができるとの報告もあります。Frontiers誌のレビュー研究では、教師教育におけるリフレクションに社会的対話を組み込む枠組みが提案されており、リフレクションを個人作業から共同学習へと拡張する動きがみられます。またICT活用も進んでおり、授業のビデオ分析によるリフレクション支援や、オンライン上でのリフレクション日誌共有などの実践研究が増えています。これらの研究から、教育分野ではリフレクションが教員養成・教師の専門性向上に不可欠であり、その指導法・支援環境・評価法について継続的に議論と検証が行われていることが分かります。
ビジネス・リーダーシップ分野におけるリフレクションの研究
ビジネスの現場でも、リフレクションはリーダーシップ開発や人材育成の手法として注目されています。特に変化の激しいVUCA時代において、経験から素早く学習し意思決定の質を高めるために、企業研修や自己啓発プログラムにリフレクションが組み込まれる例が増えています。例えばリーダーシップ研修では、参加者が現場で直面した課題を振り返り、その対応をグループで議論するケーススタディ形式がよく用いられます。これにより、リーダーは自らの意思決定プロセスを客観視するとともに、他のリーダーから多様な視点を学ぶことができます。
学術研究の観点では、リフレクションがビジネス上の成果やパフォーマンスに与える影響が実証的に調べられています。その一つに、HECパリのジャーダ・ディ・ステファノらの研究があります。彼らは研修参加者を対象に、業務課題を実施した後でわずか数分間の振り返り時間を設けるグループと、全く振り返りをしないグループを比較しました。その結果、振り返りを行ったグループは次回の課題において成績が約18%向上したことが報告6されています。この「リフレクション効果」とも言うべき結果は、忙しい業務の中で立ち止まって考える時間を取ることがいかに学習効果・業務効率を高めるかを示すエビデンスと言えます。また別の調査では、ある企業の管理職研修において、日々の業務日誌に1日15分間のリフレクション記入を課したところ、数ヶ月後に参加者の問題解決能力や自己効力感が有意に向上したという結果も報告されています。リフレクションが自己効力感(Self-efficacy)を高め、それが成長意欲や業務パフォーマンスの向上につながるメカニズムが示唆7されています。
さらに、経営者・リーダー層に焦点を当てた研究では、定期的に自己振り返りを行う経営者はそうでない経営者に比べて意思決定が戦略的になり、組織パフォーマンスも高い傾向があると指摘されています。ハーバード・ビジネス・レビューの記事によれば、優れたリーダーほど日常的に内省の習慣を持ち、そこから得た教訓を組織運営に反映させている8といいます。具体的には、自身の行動や判断を振り返り「何が効果的だったのか」「次回は何を変えるべきか」を考えることで、リーダーシップスキルや対人コミュニケーションが磨かれていくとのことです。このような知見から、近年多くの企業が1on1ミーティングやアフターアクションレビュー(AAR)などの形で組織的なリフレクションの場を設けるようになっています。リフレクションは個人の成長だけでなく、組織学習を促進し組織の適応力を高める手段としても期待されています。
医療・看護分野におけるリフレクションの研究
医療や看護の分野でも、リフレクションは専門職教育および継続的な臨床能力向上のキーコンセプトになっています。医師や看護師は日々複雑で予測不能な状況に直面するため、その経験から迅速に学習し次の判断に活かす力が求められます。医学教育・看護教育では1990年代以降、リフレクションが正式にカリキュラムに取り入れられ始め、学生が臨床実習日誌を記録して指導教官と振り返り面談を行ったり、看護基礎教育でのケースカンファレンスで内省を促したりといった実践が広がりました。日本でも2000年代初頭に看護教育へリフレクションが紹介され、基礎教育から新人研修、管理者研修まで広く活用9されています。
研究レビューによると、リフレクション能力は専門職としてのコンピテンシー(力量)の一要件とみなされており、多くの教育者が「プロフェッショナリズム養成には内省力の醸成が不可欠」と主張10しています。実際に、多くの医療系教育課程でリフレクション活動(症例日誌、ポートフォリオ、グループ討議など)が導入されていますが、その教育的効果については長らく定性的・理論的な支持が中心で、実証的エビデンスは限られていました。2009年の系統的レビューでは、「リフレクションとリフレクティブプラクティスに関する文献のエビデンスは大部分が理論的であり、教育効果を明確に測定した研究は少ない」と指摘11されています。つまり、リフレクションが重要だという認識は共有されながらも、具体的に何が有効でどのような成果が得られるかについては十分な検証の余地があったということです。
しかし2010年代以降、この状況は徐々に変わってきました。近年の研究では、例えば看護教育におけるリフレクション活動が看護学生の臨床判断力や自己効力感の向上に寄与することを示す報告12や、リフレクションを組み込んだ研修医プログラムで医療安全に関する意識と知識定着度が高まったという実験結果などが公表されています。あるレビュー研究では、公衆衛生関連職種において「リフレクションが実践の改善に繋がるという限定的ながら増加傾向のエビデンス」が示されており、まだ決定的ではないもののリフレクションが実務能力を高める可能性が支持されています。また、医学生・研修医によるリフレクティブライティング(省察的文章執筆)がプロフェッショナルアイデンティティの形成を促すという知見も得られています。2023年の体系的スコーピングレビューでは、医学教育におけるリフレクティブライティングの実践と効果について200本近い論文を分析し、構造化されたリフレクションの実施が医学生・医師の信念体系や専門職としての価値観形成に影響を与えることが示唆されました。例えば患者ケアの体験を文章に綴り振り返ることで、自身の感情や倫理観に向き合い、より成熟した専門職アイデンティティを育む効果があるという指摘です。
他方、医療分野ではリフレクションの評価方法も大きな課題でした。そこで近年は、リフレクションの深さや質を評価するルーブリック(評価尺度)や自己評価尺度の開発も行われています。例えば医学教育では学生のリフレクションエッセイを「記述レベル~批判的レベル」の段階で評点化する方法や、看護では看護学生用のリフレクション自己評価尺度を作成し信頼性・妥当性を検証する研究などが進められています。これらのツールにより、教育者は学習者のリフレクション能力の伸長度合いを把握し、適切なフィードバックを与えることが可能になります。
総じて、医療・看護分野ではリフレクションは実践知の向上と安全・質の高いケア提供に欠かせないプロセスとして位置づけられ、その教育手法や効果検証が深化しつつあります。ただし、リフレクション自体が本質的に主観的で文脈依存的な活動であるため、エビデンスに基づく教育手法として確立するにはまだ課題も残されています。
リフレクションの効果と評価に関する実証研究
リフレクションが学習やパフォーマンスに与える効果については、前述の各分野の通り個別の研究が蓄積されてきました。ここではそれらを横断的に捉え、共通して得られている知見や評価方法について整理します。
まず効果に関しては、リフレクションは学習者の深い学び(Deep Learning)に繋がることが多くの研究で示唆されています。体系的レビューによれば、リフレクションを取り入れた群はそうでない群に比べ、理解度や問題解決成績が向上する傾向がありhbr.org、この効果は自己効力感の向上を媒介として現れるとされていますcpree.uw.edu。例えば前述のディ・ステファノらの研究hbr.orgや教育分野での実験研究を総合すると、振り返りにより「自分は学べている」という手応え(自己効力感)が増すことで新たな課題にも意欲的・戦略的に取り組むようになるというメカニズムが考えられますhbr.org。これは、内省を通じて自らの成長を実感し、主体的学習者になるというリフレクションの効果を裏付けるものです。
一方で、リフレクション自体の測定・評価には課題もあります。リフレクションの質は単純なテストの得点のようには測れず、文章の内容分析やポートフォリオ評価など時間と訓練を要する方法が必要です。しかし近年、複数のレビュー研究を統合した報告では「構造化されたリフレクションは教え・学習・測定が可能である」と結論付けられています。すなわち、適切な指導のもとで学生や研修生にリフレクションの方法をトレーニングすれば、そのスキルを身につけさせることができ、しかも所定の枠組みに沿ったアウトプットをルーブリック評価することで客観的な測定も可能だということです。例えば、医学教育分野の複数の研究をまとめたレビューでは、リフレクション課題への取組みが学習成果の向上に寄与し、そのリフレクションの深さは評価基準によってある程度判定できるとしていますmdpi.com。
また長期的効果については、リフレクション習慣を身につけた人は継続的に自己調整学習を行うようになり、学習効率や業務効率が持続的に高まる可能性が指摘されています。加えて、組織レベルでもリフレクション文化の醸成が従業員のエンゲージメントやチーム学習能力を向上させるとの報告もあります。もっとも、これらの長期的・組織的な効果については定性的な観察も多く、厳密な因果関係の解明には今後さらなる研究が必要でしょう。
評価方法に関しては、前述のように文章分析による質的評価(内容を熟練者が判定)と尺度化による量的評価の両面で進展があります。質的評価では、たとえば看護教育で学生のリフレクション記録を専門家が読み取り、Hatton & Smithのレベルに照らして評価する方法が取られています。一方、量的評価としてはKemberらが開発したリフレクション尺度(経験の内省度合いを自己評価する質問票)などがあり、研究目的で活用されています。もっとも、リフレクションのように複雑で個人差の大きい現象を数値化することには限界もあり、評価者間の一致度や文化的バイアスなど課題も残ります。そのため、評価の信頼性を高める工夫(複数評価者によるチェック、ポートフォリオ全体での総合評価など)や、評価そのものが学習者の内省を深めるような形成的評価の導入が模索されています。
近年の理論的進展と議論(2010年以降)
2010年以降、リフレクション論に関する理論的な進展や新たな議論もいくつか生まれています。その一つは、リフレクションの批判的側面の重視です。従来のリフレクション実践は目の前の経験と自分の反応に焦点が当たりがちでしたが、近年は「なぜそのように感じたのか」「その背景にある組織文化や価値観は何か」といったメタ認知的・批判的問いを含めることが重要だと論じられています。これは、リフレクションを単なる内省に留めず、個人の前提や社会的文脈を検証する批判的リフレクションへ高めることが、真の行動変容につながるという考え方です。メジロー(ジャック・メジロー)の変革的学習理論においても、自己のもつ枠組みに気づきそれを再評価するプロセスが強調されており、リフレクションを通じたパラダイム転換が学習者の深い変容をもたらすとされています。
また、リフレクションの社会的・協働的次元に関する理論的発展も見られます。従来は個人の内面的プロセスと捉えられがちだったリフレクションに対し、近年の社会文化的アプローチでは「リフレクションは対話的に構成される」とする見解があります。すなわち、他者との対話や社会的な実践共同体(コミュニティ)の中で省察が共有・洗練されることで、より高次の学習が実現すると考えるものです。例えば教育学者の間では、教師コミュニティ内で互いの授業を観察し合いフィードバックを交換することで、内省が深化し専門的知見が共同生成されるという報告があります。このようなリフレクションの社会構成主義的な理解は、個人内過程としてのリフレクション観を補完し、ワークショップやコミュニティ実践への示唆を与えています。
さらに、リフレクション研究のメタな視点として、エビデンスベースと解釈学的伝統の相克が議論されています。医学教育の文脈では、反省的実践が一種の人文学的・芸術的アプローチとして発展してきた一方で、近年の教育評価の風潮は何かと数量的エビデンスを求めます。これに対し、一部の研究者は「リフレクション本来の理論的基盤を取り戻す」必要性を提起しています。Ngら(2015)は「医学教育におけるリフレクションの理論志向の再興(Reclaiming a theoretical orientation to reflection in medical education)」と題した論考で、リフレクション教育が測定とアウトカム至上主義に傾きすぎることへの懸念を示しました。つまり、リフレクションは本来、数量化できない内的洞察や意味形成のプロセスであり、その価値まで数値評価に馴染ませようとすると本質を損ないかねないという指摘です。この議論は、リフレクション教育を推進する上で定性的価値と定量的評価のバランスをいかにとるかという課題を浮き彫りにしています。
他の進展としては、テクノロジーとの融合(リフレクション支援アプリやオンラインポートフォリオの活用)、異文化間でのリフレクション解釈の違い(例えば「内省」が文化によってポジティブにもネガティブにも捉えられる点)なども議論されています。例えば日本では「内省=反省=ネガティブ」というイメージを払拭し、生産的で未来志向のリフレクション文化を根付かせることが課題とされます。一方欧米では「批判的省察(critical reflection)」の語が強調され、社会正義教育や看護倫理教育などで信念や偏見を問い直す手段としてリフレクションが語られる傾向があります。
総括すれば、2010年代以降の理論的議論は、リフレクションをより深く・広く・本質的に活用するにはどうすべきかという点に収斂しています。リフレクションは単なる流行の教育手法ではなく、人間の経験学習に関する根源的なプロセスであるため、それを教育や組織開発の中で最大限に活かすにはなお探求が必要です。今後も各分野の研究者・実践者が協力し、リフレクションの効果的な実践法と評価法を追究するとともに、その人間的価値を見失わない理論構築が進められていくでしょう。
参考文献
- knowledge.nurse-senka.jp ↩︎
- askoma.info ↩︎
- https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html#:~:text=,of%20processing%20and%20internalizing%20information ↩︎
- reflection.ed.ac.ukreflection.ed.ac.uk ↩︎
- https://www.tokushima-u.ac.jp/fs/1/9/0/5/2/8/_/Vol_10-1.pdf#:~:text=%5BPDF%5D%20%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%94%A8%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%A9%95%E4%BE%A1%E5%B0%BA%E5%BA%A6%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%20,%E7%A2%BA%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E ↩︎
- hbr.org ↩︎
- https://hbr.org/2014/04/to-enhance-your-learning-take-a-few-minutes-to-think-about-what-youve-learned#:~:text=Research%20participants%20who%20did%20an,by%20thinking%2C%20the%20research%20suggests ↩︎
- https://hbr.org/2022/03/dont-underestimate-the-power-of-self-reflection ↩︎
- https://knowledge.nurse-senka.jp/234449/#:~:text=%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%AB%96%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%84%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%A0%B4%E3%81%A7%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 ↩︎
- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↩︎
- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↩︎
- https://www.mdpi.com/2227-7102/6/3/27#:~:text=match%20at%20L1355%20Findings%3A%20Limited,5 ↩︎
- Dewey, J. (1938). Experience and Education. (経験からの学びの基盤としてのリフレクション)knowledge.nurse-senka.jp
- Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. (経験学習モデル:経験→省察→概念化→実践)knowledge.nurse-senka.jp
- Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. (専門職教育における省察的実践の提唱)knowledge.nurse-senka.jpknowledge.nurse-senka.jp
- Mann, K., et al. (2009). “Reflection and reflective practice in health professions education: a systematic review.” Adv in Health Sci Educ, 14(4), 595-621. (医療者教育におけるリフレクションのシステマティックレビュー)pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Van Beveren, L., et al. (2018). “We all reflect, but why? A systematic review of the purposes of reflection in higher education in social and behavioral sciences.” Educational Research Review, 24, 1-9. (高等教育におけるリフレクションの目的に関するレビュー)learntechlib.org
- Di Stefano, G., et al. (2014). “Learning by thinking: How reflection aids performance.” Harvard Business School Working Paper & HBR.org. (振り返りが業績向上に資することを示した研究)hbr.org
- 田村隆一・他 (2001). 「リフレクションの看護教育への導入」看護教育, 42巻 etc. (日本における看護教育へのリフレクション導入)knowledge.nurse-senka.jp
- 小山理英 (2022). 「看護におけるリフレクションの概念分析」伝統医療看護連携研究, 3(2), 102-113. (看護領域におけるリフレクション概念の定義と属性)jstage.jst.go.jp
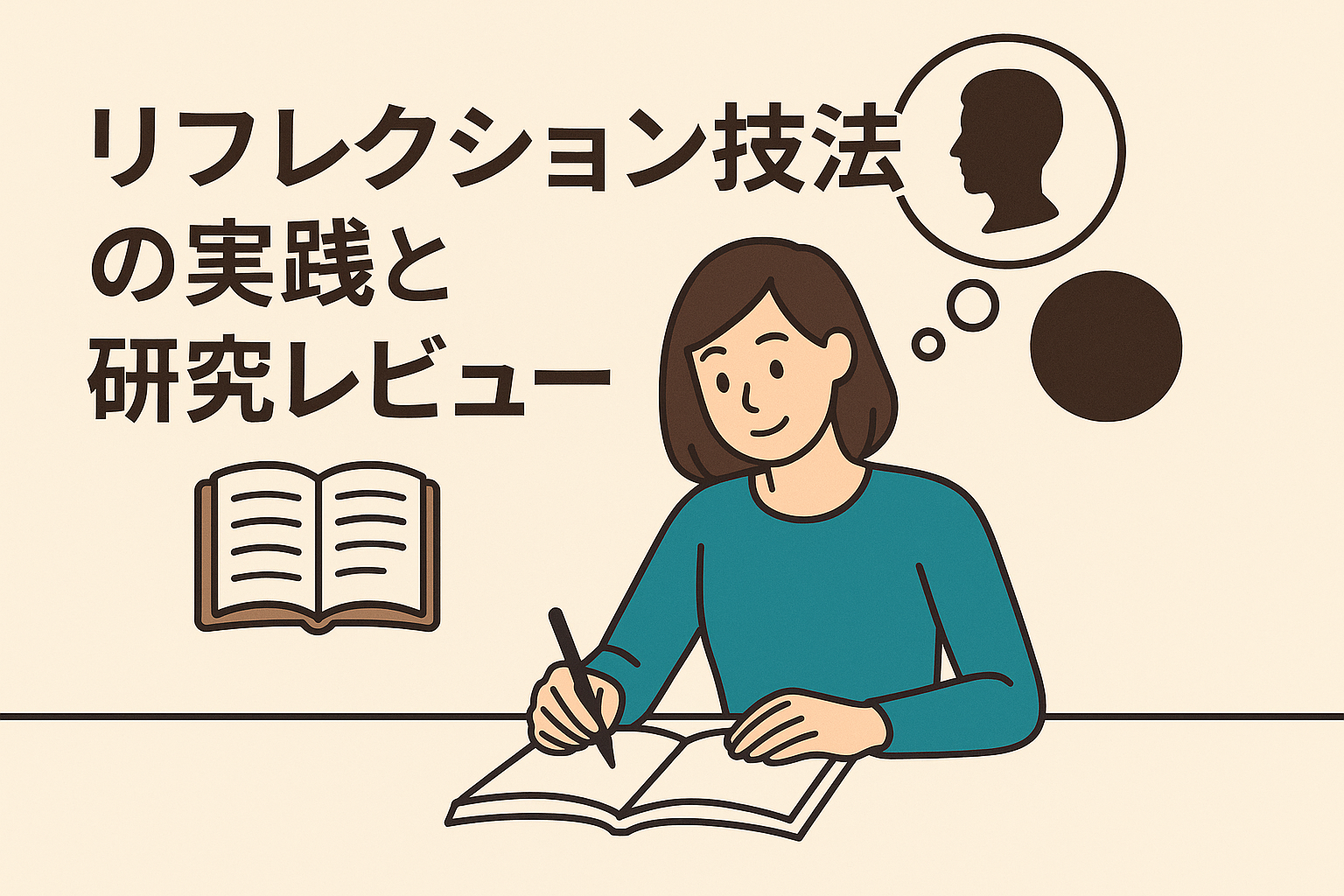
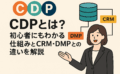

コメント