この記事はこんな人におすすめ
- コンサルタントを目指す人、若手コンサルタント
- 「問題」と「課題」の違いを知りたいビジネスパーソン
- 経営改善や業務改革が表面的になっていると感じるマネージャー
- 問題解決フレームワークを体系的に学びたい人
記事の概要
コンサルティングの現場では「問題」と「課題」を混同すると解決策が的外れになりがちです。
- 問題=現状(As-Is)と理想(To-Be)の間にあるギャップ
- 課題=問題を解決するための取り組みテーマ
問題を正しく定義できるかどうかが、戦略の成否を左右します。
Before / Afterで分かる「問題」の定義の力
| Before | After |
|---|---|
| 問題と課題を同じ意味で使っていた | 両者の違いを明確に説明できる |
| 対処療法的な施策が多い | 本質的な問題にアプローチできる |
| 会議で論点が散らかる | 問題定義があることで議論が収束する |
問題とは?(定義)
問題とは「現状と理想の差分(ギャップ)」を指す。下記添付画像の赤色でGAPと書いてある箇所です。
色々定義がありますが、私がコンサルティングする際は下記のように考えます。
問題解決と言いますが、実際には「問題=現象」を指していることが多いように思えます。
大事なのはその現象を生じさせている要因を複数考えて、その要因を解決するための課題設定です。
要因や課題は複数あるのですが、中でも自社の限られたリソースの中で何を解決することが最も効果があるのか?を考えて取り組むことが大事です。
問題の要因をあぶり出すには、経験値が必要ですが、基本的にはなぜ?(Why)を繰り返すことで真因まで辿り着きます。これも闇雲にやるのではなく確度の高い仮説(仮の答え)があると効率化されます。
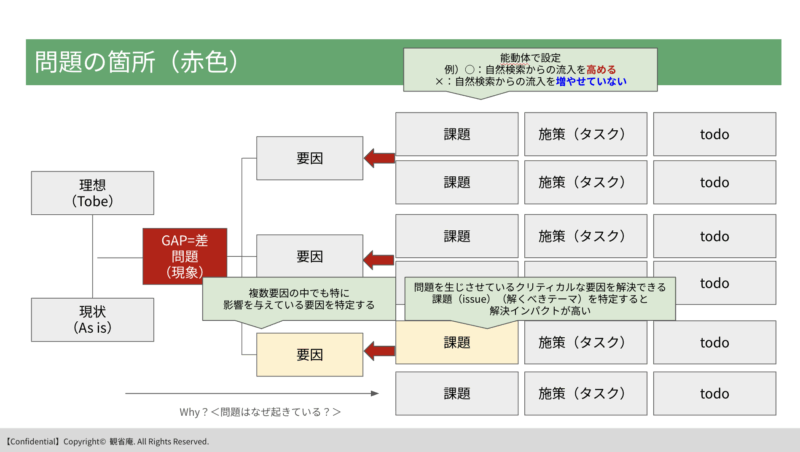
問題解決型アプローチの例
問題定義から施策実行までの流れ
- 理想:市場平均成長率に合わせて10%成長
- 現状:売上が前年同期比で横ばい
- 問題:売上成長が市場に追いついていない(左だけでは単なる現象)
- Why?を仮説ベースで考えます。今回は4Pで考えます。
- 要因仮説
- Product:新規商品の開発速度が遅い
- Price:割引が多く、売上がのばせられていない
- Promotion:上期の宣伝効果が落ちている
- Place:販売経路が限られている
- 上記に対して仮説の分析を行いPlaceについて事実だとします。
- さらに深掘りし、販売経路が限られている要因はなぜ?か考えます。
- ロジックツリーやMECEを意識します。
- 例)リアルorEC、BtoC、BtoB、新規、期村などの切り口で要因を掴みます。
- ロジックツリーやMECEを意識します。
- 分析の結果今回の場合、「特にBtoBの新規加盟が獲得できていないうえ、離脱が増えている」ということが真因だとしましょう。
- 真因と特定されれば、それを解決するための課題は「BtoBの販売経路を拡大する(には?)」という解くべきテーマ「課題」が決まります。
- 課題の粒度はさらに分解して新規獲得、離脱防止に分けていきます。
- 次に課題に対してインパクトのある施策を選びます
- インパクトのある施策の優先順位はQ(質)、D(実行しやすさ)、C(コスト)などで絞ります。今回は新規獲得よりも離脱防止がDとCの観点から有効だと判断します。離脱防止のための施策(タスク)を洗いだします
- タスクを実行するとなったら、実際には調査や、ヒアリング等細かいやるべきこと(todo)が見えてくるので、それをメンバーに割り当ててtodoを実行していきます
- これがいわゆる「施策実行」になります。
- タスクを実行するとなったら、実際には調査や、ヒアリング等細かいやるべきこと(todo)が見えてくるので、それをメンバーに割り当ててtodoを実行していきます
- 課題の粒度はさらに分解して新規獲得、離脱防止に分けていきます。
- 真因と特定されれば、それを解決するための課題は「BtoBの販売経路を拡大する(には?)」という解くべきテーマ「課題」が決まります。
- さらに深掘りし、販売経路が限られている要因はなぜ?か考えます。
問題と課題の違い
| 項目 | 問題 | 課題 |
|---|---|---|
| 定義 | 現状と理想のギャップ | 問題を解決するための取り組みテーマ |
| 抽象度 | 高い(全体的・本質的) | 具体的(テーマ・行動指針) |
| 例 | 売上が市場成長に追いついていない | 新規顧客開拓チャネルの強化 |
「問題の定義」なくして「課題設定」は成立しません。
コンサルティングにおける問題定義の重要性
- 論点の絞り込み
- 議論を「本質的な1点」に集中できる
- 資源配分の最適化
- ヒト・モノ・カネを真の問題解決に投資できる
- 戦略ストーリーの一貫性
- 問題定義があるからこそ、課題 → 施策 → 成果につながるストーリーが描ける
問題を抽出するフレームワーク
- ギャップ分析:As-IsとTo-Beを比較
- ロジックツリー(Why-Tree):「なぜ」を繰り返して根本原因を探る
- MECE:漏れなく・ダブりなく要素を分解
- 3C分析・5Forces・SWOT:外部・内部環境から「解くべき問題」を整理
活用事例
事例1:製造業の収益低迷
- 問題:原価率上昇により利益率が低下
- 課題:購買コスト削減、工程改善
事例2:小売業の顧客離れ
- 問題:リピート率が市場平均を下回る
- 課題:会員制度の強化、顧客データ活用
事例3:IT企業の採用難
- 問題:必要なエンジニアを確保できない
- 課題:採用ブランド構築、リファラル採用の導入
よくある質問(FAQ)
Q1. 問題は必ず数値化すべき?
→ はい。数値化すれば曖昧さが消え、共通認識を持てます。
Q2. 問題定義に時間をかけすぎると遅れませんか?
→ 表面的な課題に飛びついて時間とお金を浪費するより、最初に定義を固めた方が最終的に早く解決できますし、インパクトがでます
Q3. 問題解決と課題解決の違いは?
→ 問題解決=ギャップを埋めること。課題解決=そのためのアクションを完了すること。
まとめ
- 問題とは「現状と理想のギャップ」
- 課題は問題を解決するためのテーマであり、両者を混同しないことが重要
- 問題定義が正しくできれば、戦略・施策が一貫して成果につながる
- コンサルティングでは「問題の定義」こそが最も価値あるプロセス
参考書籍
イシューについて詳しく解説されています
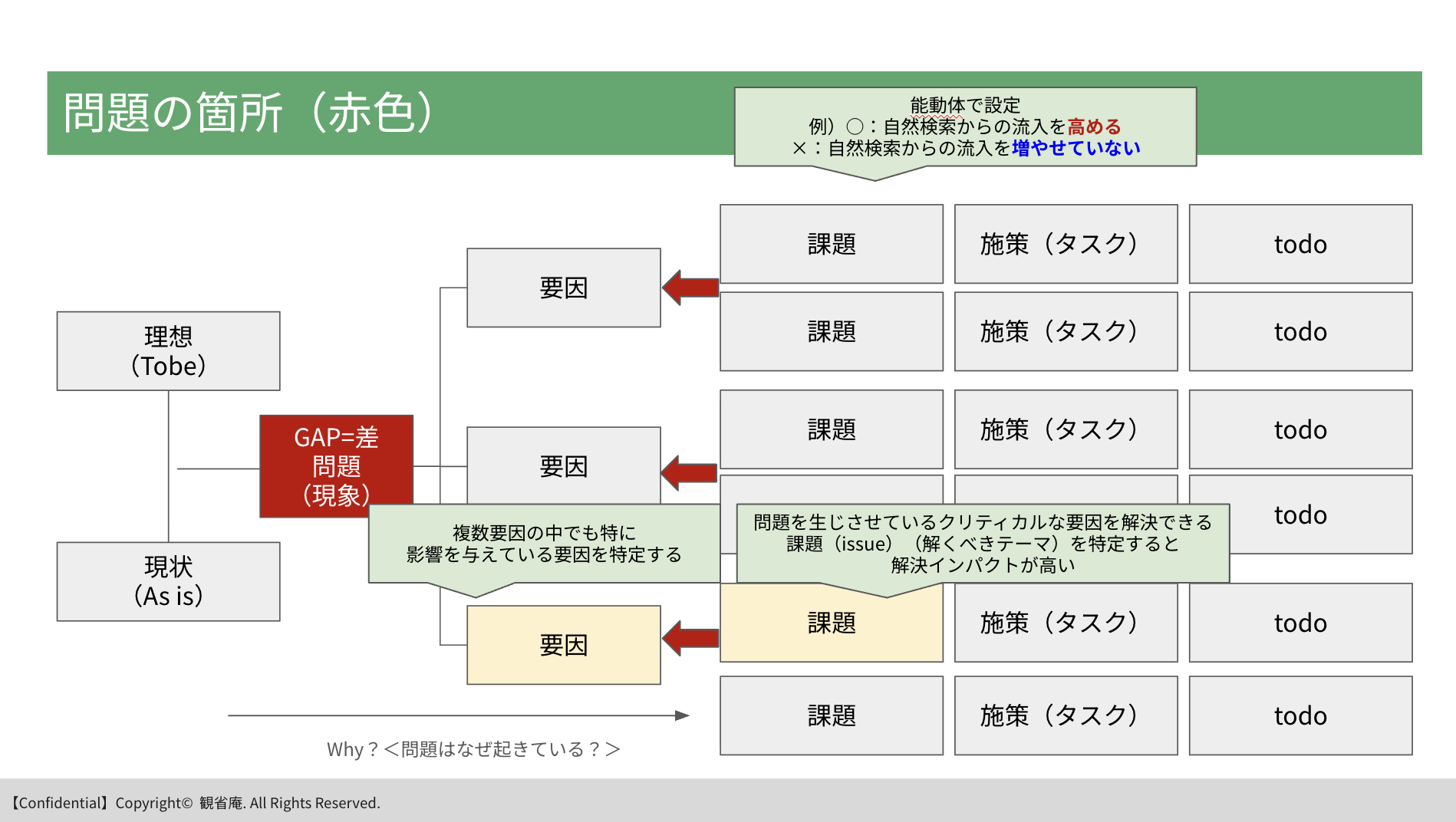


コメント